10冊以上買うと、なんとなく出版社ごとの傾向が見えてきます。
うちのお気に入りである学研と成美堂出版をはじめ、KUMONや文理出版など、手元にあるドリルを比べて私からみた特徴を書いてみます。
ドリル選びの時に少しでもお役に立てたら嬉しいです。
出版社ごとの傾向
どのドリルにもできたよ!シールやがんばりシールなど、各ページごとに終わったら貼れるシールはあります。
以下は、あくまでも私の独断なので、そういう見方もあるんだ程度で軽く読んでくださいね。
KUMON くもん出版
うちの息子が解き終わったドリルも書いておきます。
すくすくノートシリーズとはじめてのおけいこシリーズは体系自体が異なるみたいです。ドリルの見た目、サイズ、中身の印象も違います。
はじめてのシリーズの方がカラフルで子供受けしやすい雰囲気です。パッと見で子どもが1人でサラサラ解けるタイプだと思います。
ただ、あまり楽しさが重視されていません。はじめてのおけいこシリーズには「ちえ」もなく、「えいご」、「もじ・ことば」、「かず・けいさん」、「めいろ」、「こうさく」の5シリーズみです。
ある意味子供に媚びない、お勉強のための作りだと思います。
カタカナをやらせた感想⇒5歳男児、ドリル一冊でカタカナをマスターする
GAKKEN 学研
息子のお気に入りの出版社で本屋で注文して取り寄せたものもあり、沢山解いています。
- 4〜6歳 アルファベット ABC (学研の幼児ワーク) [ 学研の幼児ワーク編集部 ]
- 5歳 ひらがな ことば (学研の幼児ワーク) [ 学研の幼児ワーク編集部 ]
- 6歳 もじ かず ちえ (学研の幼児ワーク) [ 学研の幼児ワーク編集部 ]
- 4〜6歳 こうさく (学研の幼児ワーク) [ 学研の幼児ワーク編集部 ]
- でんしゃの かず・とけいれんしゅうちょう 7さいまでに楽しくおぼえる (学研の頭脳開発) [ 「学研の頭脳開発」編集部 ]
- 入学準備さんすう 入学後の自信につながる (学研の頭脳開発) [ 親野智可等 ]
こちらも複数シリーズがあるようで、学研の幼児ワークと学研の頭脳開発シリーズは別物です。
問題文をきちんと読まないと答えが出ない問題があり、テスト勉強への入り口という感じもします。
「でんしゃの~」は文字通り、息子が電車に惹かれて買いました。電車関連の内容が盛りだくさんで、電車好きのお子さんは飛びつくかもしれません。すうじから足し算、時計までありますが、電車の特集ページなどもあり、内容は薄めです。
幼児ワークシリーズはとにかくカラフルで可愛いです。子供が楽しそうにワークを開きます。
1ページあたりの問題数は少な目な気がします。
幼児ワークシリーズは入り口となる「はじめて」のほか、文字・数・知恵の「総合ワーク」、平仮名・カタカナ・漢字の「もじ」、数・計算・時計の「かず」、「めいろ」、「ちえ」、工作・英語の「その他」のシリーズに分かれています。
最近は新しいドリルを買う前に子供自身が学研の幼児ワークの裏表紙を見て、欲しいものを仮決めしてから本屋に行くほど、子供にとっては楽しいようです。
成美堂出版
小さめの本屋には置いていなくて、大型書店で見つけました。
成美堂自体は複数シリーズ出していそうなのですが、近くの大型書店には、はじめてのえんぴつちょうシリーズしか置いていませんでした。東北大学教授監修がうりのようです。ただ、同じシリーズなのに絵柄の雰囲気が異なっていて違和感があります。
「かんじ」より「ちえ」の方が難しく、間違い探しが見つからずに悔し泣きをしだしたこともありました。こちらも問題文を読むくせがつけられそうです。
文理出版
「くりかえし」とあるように、本当にくりかえして書かせるドリルです。ちょっとした絵とかはありますが、とにかく書かせます。点つなぎや数字比較の迷路などはあります。
ある程度忍耐力のあるお子さんに綺麗な数字を書かせる際に向いていると思います。⇒10冊以上買った幼児用ドリルのなかで唯一失敗した!と思った1冊
番外編 七田式ドリル
右脳が育つとかで凄いやらせてみたかったのですが…何度見せても、子どもが買うと言い出しませんでした。
必要最低限、子供が分かるように絵柄にしてあるだけというか、色遣いといい絵のタッチといい、子どもに1ミリも媚びていません。
あくまで親が買って子供にやらせるというスタンスなのかもしれません。
やらせてみたかった…。
まとめ
能力を効率的に伸ばすという観点では違くなるかもしれませんが、子供が楽しむという意味では「学研>成美堂出版>くもん出版>文理出版>七田式」だと思います。
息子が解くのを見ていた感じ、初めはあまり背伸びして難しいものを与えない方がよさそうです。
やりたいと言い張ったので買ってあげた漢字は、難しいと言っていて、ちょっと辛そうでした。一応、「漢字は小学生のお兄ちゃんお姉ちゃんがやるものだもの。難しくてあたりまえだよ!年中さんでここまでできるなんてすごいよ!」とフォローを入れておきました。
「出来ない」「分からない」「面白くない」という体験を幼児期に積ませてしまうと、勉強が嫌いになりかねないと思います。
ドリルに書いてある対象年齢を目安に、なるべく初めは簡単そうな、楽しそうなドリルを選ぶのがおすすめです。⇒子供が熱中した幼児用ドリル・ワーク2冊
5歳の子供を勉強好きにさせた方法⇒5歳児が「お勉強楽しい!」って幼児用ドリルやワークをするまでにやったこと
結果的に半年でどのくらいお勉強ができるようになったか⇒5歳児の学力



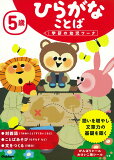

コメント